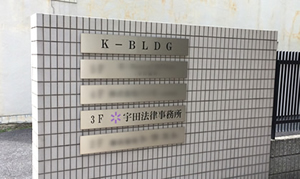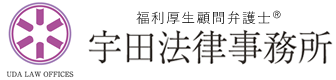公正証書遺言作成における必要書類
どのような遺産を誰にどれだけ相続させるのか、被相続人の意思を尊重するために作成される遺言書の中には、公正証書遺言というものがあります。
遺言には上述のように相続人に大きな影響を与えるものであるため、遺言を公証人に作成させることで、方式不備による遺言の無効のおそれや、原本の紛失・隠ぺい・改ざんのおそれがなくなります。
また、相続人が遺言を発見しなければ、遺言の存在に気が付かないこともありますが、公正証書遺言は、遺言検索サービスによって検索ができるため、存在の有無を確認することが容易となります。
このページでは、相続問題において重要な役割を持っている公正証書遺言を作成するに際して必要な書類とその収集方法についてご紹介します。
公正証書遺言作成の必要書類
①遺言者本人の身分確認資料
ここでいう身分確認資料とは、運転免許証等の公的機関が発行している証明書のことをいいます。
印鑑登録証明書を使うこともできますが、市区町村役場で現在300円の交付手数料を支払って受け取ることとなります。
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
戸籍謄本とは、戸籍の全体の写しをいい、遺言者と相続人の間柄がわかるように、戸籍謄本を取り寄せることになります。
これも、市区町村役場で取り寄せることができ、交付手数料として現在450円・改正原戸籍謄本は750円がかかります。なお、後述する住民票と戸籍謄本は、弁護士は職務上請求という形で取り寄せることができます。
③必要に応じて遺贈を受ける人の住民票
法定相続人以外の者に対して遺産を相続させたいような場合には、同遺贈を受ける者の住民票を用意する必要があります。
住民票も市区町村役場において現在は、300円を支払って交付を受けることになります。
④遺産の中に不動産がある場合の必要書類
遺産の中に不動産がある場合には、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が必要となります。
不動産登記事項証明書は、法務局において1通600円で交付を受けることができます。
固定資産評価証明書は、市区町村役場で200~400円程度で交付を受けることができます。
⑤預貯金等の通帳・コピー
銀行等の預貯金口座を特定するために必要であるため、預貯金の通帳やそのコピーが必要となります。
ご自身で預貯金通帳をコピーすることが可能です。
⑥証人の確認書類
公正証書遺言を作成する手続きの中では、証人を2名おく必要があります。
そして、証人を自身で用意する場合、証人の確認証として、住所・氏名・生年月日がわかる、運転免許証のコピーが必要となります。
なお、証人には公平性が求められるため、法定相続人や受遺者・それらの配偶者等、未成年は証人になることができません。
⑦遺言執行者の特定資料
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する責任を負うもので、遺言者が遺言執行者を指定することができます。
そして、証人同様に、住所や氏名・生年月日がわかる資料を用意する必要があります。
なお、証人と異なり、相続人やその配偶者であっても遺言執行者になることができ、相続人や受遺者が遺言執行者となる場合には、上記資料を用意する必要はありません。
相続問題にお困りの方は宇田法律事務所までご相談ください
以上のように、公正証書遺言は、その内容の信用性が制度的に高く、紛争が生じた場合に果たす役割が極めて高い公正証書といえます。
そのため、手続きは法律の定めるところにしたがって厳格に行われ、必要となる資料も多岐にわたります。
まずは、公正証書遺言を作成したい理由を含め、弁護士に相談をして、そのうえで必要な手続きや、資料の収集について助言を求めることが有効といえます。
弁護士は、これらの分野について専門的な知見を有しているため、有意義な助言を得ることが期待できます。
宇田法律事務所は、相続に関する法律問題を取り扱っております。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続人が行方不明で連...
遺産分割協議を進めるには、相続人全員が参加する必要があります。しかし、行方不明の[...]

-
離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目[...]

-
過失割合
■過失割合事故が発生した場合、原因が加害者のみにあるとは限りません。このような場[...]

-
相続人不存在とは?財...
この記事では、相続をする人がいない状況で被相続人が亡くなってしまった場合に残され[...]

-
【オーナー様向け】賃...
店舗やテナントなどを賃貸している建物のオーナーの方から、賃借人から立ち退きを拒否[...]

-
婚姻費用分担請求
「配偶者に離婚したい旨を伝えたところ、別居されてしまい、それから生活費をもらえず[...]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |