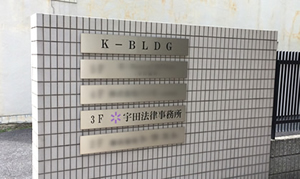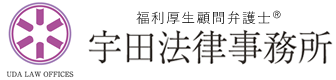遺留分の計算方法
■遺留分の計算方法
まず、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。「遺留分の基礎となる財産」は、被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与した財産を加えた額から債務を差し引いて算定します。
そして、その「遺留分の基礎となる財産」に遺留分の割合をかけた額が、遺留分として請求することができる金額となります。
遺留分の割合については、以下の通りです。子や直系尊属が複数人である場合は、その都度人数で割ることになります。
・相続人が配偶者のみの場合・・・配偶者: 2分の1
・相続人が子のみの場合・・・子:2分の1
・相続人が直系尊属のみの場合・・・直系尊属:3分の1
・相続人が配偶者と子ども1人の場合・・・配偶者: 4分の1、子ども:4分の1
・相続人が配偶者と直系尊属・・・配偶者: 3分の1、直系尊属:6分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者:2分の1(兄弟姉妹に遺留分は認められていない)
具体例とともに計算してみましょう。
父が亡くなり、妻と実子2人(長男、次男)が相続人であるが、遺言で、遺産総額4000万円の預金を長男1人が相続することになっていた場合
→妻の遺留分が4000×4分の1=1000万円、実子の遺留分が4000×4分の1=1000万円となり、長男と次男で2分の1ずつとなるため、次男の遺留分は1000×2分の1=500万円となります。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺贈と遺留分の関係はどうなるのか」、「特別受益の持ち戻しとは何か」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続権のない連れ子に...
連れ子がいる状態で婚姻をした場合には、結婚相手と子どもとの間には相続権が発生しま[...]

-
【売主様向け】契約不...
契約不適合責任の免責とは、売主が不動産の売買契約において不動産売却後の保証責任を[...]

-
底地・借地権トラブル...
借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの[...]

-
離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目[...]

-
B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1[...]

-
土地の境界線
自分の土地と隣の人の土地との境界が不明確になっている場合、以下のような手段を採る[...]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |