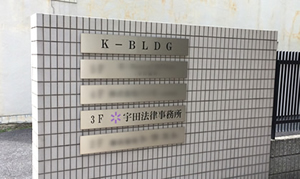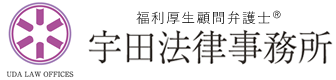遺言書の効力に関する基礎知識
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されますが、以下、具体的な遺言書の効力について、主な効力である5つについて概説していきます。
①相続分の指定(民法902条)
遺言者は、遺言書によって、どの相続人が、いくら相続するのか、その相続分の指定を行うことができます。これは、相続人全員分について指定することもできますし、一部の者についてのみ、指定することもできます。なお、遺言書による相続分の指定がなされなかった場合には、法定相続分(900条)によって、各相続人の相続分が決まります。
②遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止(908条)
遺言者は、遺言書によって、遺産分割方法の指定をすることができます。すなわち、具体的に言えば、相続人Aは、甲土地を、相続人Bは、乙土地を、相続人Cは、預貯金を、それぞれ相続する、などと、相続人らが、どのように遺産を分けるかについて、具体的に指定することができます。
また、遺言者は、遺言書によって、5年を超えない期間は、遺産の分割を禁止することもできます。
③遺贈(964条)
遺言者は、遺言書によって、遺贈をすることができます。遺贈とは、(基本的には)法定相続人以外の者に対して、遺言書によってする贈与のことです。
④推定相続人の廃除(893条)
遺言者は、遺言書によって、推定相続人、すなわち、遺言者が死亡した場合には、相続人となることが予定されている者を、廃除、すなわち、その者の相続権を剥奪することができます。もっとも、いかなる場合にも遺言による廃除が認められている訳ではなく、892条所定のような非違行為が推定相続人に認められるような場合でないと、廃除は認められません。
⑤遺言執行者の指定(1006条)
遺言者は、遺言書によって、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を」する者のことで(1012条1項)、平たく言えば、相続財産の管理及び相続にかかる手続を行う者です。
以上が、遺言書の主な5つの効力ですが、遺言書は、法定の様式を守っているか、また、相続人の遺留分は侵害していないか、という点には注意が必要です。
宇田法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
専業主婦でも親権は獲...
夫婦が離婚する際、問題となるのが「子供の親権問題」です。そして、離婚問題の中には[...]

-
安城市の相続は宇田法...
相続問題は誰もが一度は直面するであろう重大な問題です。 しかしながら相[...]

-
慰謝料・損害賠償
■慰謝料・損害賠償・慰謝料とは損害賠償を受けることができる項目は、財産的損害と精[...]

-
子供の養育費
「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を[...]

-
公正証書遺言作成にお...
どのような遺産を誰にどれだけ相続させるのか、被相続人の意思を尊重するために作成さ[...]

-
債務整理をするとロー...
■債務整理とは債務整理とは、支払えなくなった借金を減額したり、なくしたりして、負[...]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |