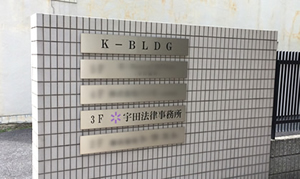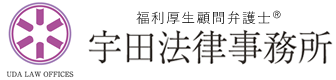遺言書 無効
- 遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されるこ...
- 成年後見制度
遺産分割協議は法律行為であることから、意思能力を欠く者が参加しているとその効果が無効になってしまいます。ここで成年後見制度を利用し、遺産分割協議を有効に行うことができます。もっとも、成年後見人と成年被後見人が共同相続人となった場合には、成年後見人のために特別代理人を選任する必要があります。 宇田法律事務所では、名...
- 借地権とは
そして、仮にこれより短い期間を契約で定めたとしても、それは無効となり(9条)、一律30年となります。また、借主は、契約期間満了による立ち退きの際に、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。 このように、借地借家法の適用を受けることは、借主は恩恵を、貸主は規制を受けることになるため、重要なのです。
- ヤミ金被害
この、民法708条に規定のある不法原因給付という制度の趣旨は、自ら社会的に非難される行為をした者は、その行為の無効を主張して法による助力を得ることはできないという、いわゆるクリーンハンズの原則にあるとされます。したがって、前述のように違法な金銭の貸し付けをしたヤミ金融に対して、借りたお金は返済する必要がありません...
- 示談交渉
そして、示談の効力は民法の規定に即して成否が判断されることになるため、和解内容に錯誤が生じている場合は、錯誤無効(民法改正後は取消し)を主張することになります。もっともここで、和解における錯誤について規定した民法696条との関係が問題となりますが、判例によって、争いの目的とならない事項について錯誤がある場合は、6...
- 遺言書の効力に関する基礎知識
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されますが、以下、具体的な遺言書の効力について、主な効力である5つについて概説していきます。 ①相続分の指定(民法902条)遺言者は、遺言書によって、どの相続人が、いくら相続するのか、その相続分の指定...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【被害者側必見】物損...
交通事故の被害に遭ってしまい、その場では特に外傷や痛みなどがなかったため、物損事[...]

-
遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を[...]

-
民事再生(個人再生)...
民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図る[...]

-
家賃値上げ交渉の進め...
土地の価格が上昇し、近辺の住宅に比べて家賃が低い場合など、家主としては家賃の引き[...]

-
ヤミ金被害
いわゆるヤミ金融とは、貸金業登録をせずに、著しく高い金利を付して金銭を貸し付ける[...]

-
債務整理をするとロー...
■債務整理とは債務整理とは、支払えなくなった借金を減額したり、なくしたりして、負[...]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |